▪演奏会当日配布パンフレットより
ドビュッシーは語る
川上哲朗(フルート奏者)
2005年の秋、私が初めて彼の部屋を訪ねた時、たしか横山氏は《ピアノのために》を弾いていた。12年の時を経て今や横山博は、誰もが認めるチェンバリスト/オルガニストになってしまった。ピアニスト時代の彼とは、シューベルト、リヒャルト・シュトラウス、ラヴェル、プーランクからデュティユーなど様々な曲を一緒に演奏したのだが、彼は常に音楽に対して通り一遍な美しさよりも、真実性(オーセンティシティ)、現実性(リアリティ)を強く求めていた。 彼は古楽の道へ、私はジャズの道へと違う道を歩み始め、暫く共演が途絶えた。彼のモーツァルトのピアノ・ソナタ全曲演奏が終わった後、ヴァイオリン・ソナタ集(パリ・マンハイムソナタ集全6曲)をフルートとピアノで演奏させてもらった。当時彼は、モーツァルト演奏における装飾やアーティキュレーション、即興演奏の歴史的正当性を熱心に調べていた。歴史的情報に基づく演奏を尊重する彼の態度が、それまでの感覚的なものから、もはや確信的なものに進化していたことに私は驚きを隠せなかった。横山博は曖昧表現を塗り重ねるレガート奏法とは早々と縁を切っていた。チェンバロやクラヴィコード、パイプオルガンなどの古楽奏法によって裏付けられた、喋るような音楽、物事を伝えるための明確な意味と情報を持つ、まさに「言語としての音楽」をそこに聞いたのである。
1913年、クロード・ドビュッシー[1862-1918]自作自演による、《夢想》《2つのアラベスク》《子供の領分》《前奏曲集第1集(抜粋)》がウェルテ・ミニョン社製のピアノロールへの収録が行われた。ピアノロールとは、リプロデューシングピアノと呼ばれる自動演奏専用の再生用ピアノのために開発された紙製のロール(巻き紙)にインクによって記録され、その印字された部分に専門の技師が穴を開け、オルゴールの様な仕掛けで再生される。リプロデューシングピアノが再現する演奏の「音量」「テンポ」「ペダリング」の再生能力については信頼できない部分があるものの、ドビュッシー自身が署名をして、発売を許可したそのロールには、ドビュッシーのピアノ奏法による「間合い(息継ぎ)」「ルバート(テンポコントロールのさじ加減)」「アルペジオ(楽譜には書かれていない和音のばらし具合)」がはっきりと刻印されている。今回、横山氏はそこに聞かれるドビュッシー独得の微妙な節まわしを手本として、可能な限りそのニュアンスを自身の演奏に反映したいと語っている。バロック期の作曲家フレスコバルディやフランソワ・クープラン等の記した「譜面に表しきれない細やかな表情は、演奏者の良い趣味に委ねるしかない」といった演奏者への助言(ある種の諦めの文句)に比べれば、ピアノロールに記録された作曲者自身の演奏には、極めて多くの情報が含まれているというわけだ。
ドビュッシーが、フレデリック・ショパン[1810-1849]の孫弟子にあたることも忘れてはならない。彼が若い頃にピアノの指導を受けたのは、ショパンの弟子であったモーテ・ド・フローヴィル夫人である。ドビュッシーは彼女のレッスンを通じて、「ショパンは練習の時にペダルは使わず、人前で演奏する際も最小限にペダルを用いること、ちょうど言葉を話すときの息継ぎとか、文法上の句読点のように扱うことを望んでいた」ことを学び、晩年にいたるまでショパンの残したピアノ演奏技法の伝統を高く評価していた。ダンパーペダル(延音ペダル)という機構を持たないチェンバロ(フランス語ではクラヴサン)という楽器を演奏する者にとって「ペダルでごまかす」という発想は存在しない。その代わりに、微細なアクセント(語調、強調)やアーティキュレーション(発音)の具合、固定された音価にとらわれない柔軟性をもったイントネーション(抑揚)など、語学の発想によって音楽を表現することが求められる。
「本当のところ、ペダルの乱用は、技術の不足を隠すための手段にしかすぎないのだろう。だから、自分が細切れにしている音楽を、誰も聞くことができないように、たくさん騒音をださなければならないのだ。」(クロード・ドビュッシー)
古楽演奏における重要な要素の一つに音楽修辞学(レトリック)というものがある。これは、古代ギリシャ・ローマにおける雄弁術や弁論術(それは身振り手振り、発声法の技術でもあった)に由来する、様々な具体的意味を持った音型(フィグール)によって音楽表現の効果を高めるための技法である。横山博が音楽修辞学をドビュッシーにも適用しようという試みは、決して奇抜なアイデアなどではなく、むしろドビュッシーが用いた音楽言語への抜け道となるはずだ。
19世紀末からドイツにおいて、音楽に物語性を強く求める「楽劇」「交響詩」というジャンルが最盛期を迎えていた。ドビュッシーの作曲技法に関する興味は(当時の)現代ドイツ音楽への憧れから始まっている。しかし、「気狂いじみた熱狂を抱いて」さえいた楽劇《トリスタンとイゾルデ(1865)》の作曲家リヒャルト・ワーグナー[1813-1883]に対しても次第に批判的になり、「詩に追随する音」に疑問を抱くようになる。フランツ・リスト[1811-1886]が先導し、リヒャルト・シュトラウス[1864-1949]で頂点に達していた一連の交響詩に対しても、そのあまりに描写的な音楽に眉を潜めている。その疑問への一つ の答えが歌劇《ペレアスとメリザンド(1902)》であり、交響詩《海(1905)》である。一般に「印象主義」と言われることの多い ドビュッシーだが、モネ、ルノアールといった印象主義の画家よりも、むしろ詩人のマラルメ、ボードレールなどに代表される「象徴主義」に傾倒していた。象徴派詩人たちの、饒舌(じょうぜつ)であることを好まず、色彩とともにニュアンスと静謐(せいひつ)を重んじるスタイルから多大な影響を受けている。「象徴派」という言葉がクラシック音楽の世界で用いられることは少ないが、エリック・サティ [1866-1925]とドビュッシーだけがそこに通じていた。
ドビュッシーが起こした“愛”に纏(まつ)わる様々なスキャンダルをここに書く余裕は無いが、9年間(1893年から1902年)にも及んだ《ペレアスとメリサンド》作曲の時代を経て、駆け落ち同様に2番目の妻エマ・バルダックと1905年に結婚した。シュシュ(キャベツちゃんという意味の愛称)と呼んだ一人娘が生まれた頃からドビュッシーはすっかり大人しい人物になったようだ。そして、愛してやまない娘のために《子供の領分(1908)》というピアノ音楽史に輝く傑作まで書き上げた。《Children’s Corner※》というタイトルはドビュッシーが尊敬するロシア人作曲家モデスト・ムソルグスキー[1839-1881]の作った連作歌曲《子供部屋(1872)》に対する賛辞(オマージュ)であろう。
ムソルグスキーの「子供部屋」には、就寝前のちいさな女の子の祈りがある。そこでは、子供の仕草やその魂の微妙な動揺が、そして大人の前で幼女が見せるポーズの得もいわれぬ様子すら、ほかの音楽には見出せない一種の熱っぽい真実な語調で、音符にされている。
※ 表題・曲名がフランス語ではなく全て英語で書かれているのは、妻の英国趣味への“からかい”だと言われている。シュシュの部屋にはイギリスの版画が飾られ、家政婦はイギリス人だった。
幼い少女が嫌々練習する難しい練習曲からの現実逃避(グラドゥス・アド・パルナッスム博士)、恋する人形(人形のセレナード)に、深刻なトリスタンをクスクス笑いでからかう(ゴリウォーグのケークウォーク)。発売された初版楽譜の扉には英語ではなくフランス語で「父親の優しい言いわけをそえて,大事なかわいいシュシュへ (A ma chère petite Chouchou, avec les tendres excuses de son Père pour ce qui va suivre)」という献辞が添えられている。これは不自然なほど大きなイタリック体で印刷されており、横山氏は、これはまるで広告用キャッチコピーのようだと語っている。
1901年以降、ドビュッシーは自らを反好事家八分音符氏(ムッシュー・クロッシュ・アンティディレッタント)と称して評論活動も行っていた。そこで彼は常に懐疑的であり、皮肉と逆説を用いて、人を煙に巻くような煩わしい物言いばかりをしている。しかしルネサンス、バロック音楽の大作曲家に対して彼は賛美を惜しまない。特に、バッハへの愛は少年のころから終生かわることはなかった。
「バッハの音楽には、あの〈音楽のアラベスク〉、というよりむしろ芸術のあらゆる様態(モード)の根底である〈装飾〉のあの原理が、ほとんど無疵(むきず)なままで見出される。」(クロード・ドビュッシー)
室内楽や管弦楽曲において大いに個性的な曲を書き上げる中、意外にもドビュッシーはピアノ曲の発表には慎重だった。《2つのアラベスク(1890)》は、マスネ[1842-1912]風の甘味な旋律線と、クープラン風の曲線的装飾によって非常に精密に組み立てられている。機能和声へのちょっとした反抗は、ロマンティックなサロン文化からの脱却を望んでいるようにも見える。その反抗心は、《アラベスク》のたった2年後、オーケストラを使って《牧神の午後への前奏曲(1892)》という、より近代的な作品として結実することになる。フルートが提示する曲線的なアラベスク風の主題(アラベスクとはもともと、植物や動物の形を基にして反復して作られるイスラム美術様式の唐草模様など)の、その最初のC♯音で近代音楽の扉は開かれた。ワーグナーの《トリスタンとイゾルデ前奏曲》で「崩壊」しはじめた機能和声から、《牧神の午後への前奏曲》は、《トリスタン》とは異なった手法で離れようとしている。あらゆる面で近代的(モデルヌ)な作品であるが、皮肉にもその影響は遥か昔の、遠いところからやってきた。1889年、1990年のパリ万国博覧会で見聞きした、東南アジアや日本を始め、世界各国の伝統芸術はドビュッシーに計り知れない影響を与えた。一方その頃、モーリス・ラヴェル[1875-1937]は、同じ古代ギリシャをテーマにしたバレエ音楽の大作《ダフニスとクロエ(1912全曲初演)》を準備していた。本日演奏されるラヴェル編曲の4手連弾版《牧神の午後への前奏曲(1910編曲)》が《ダフニスとクロエ(ピアノソロ及び2台ピアノ版)と並行して編曲されていたというのは偶然ではない。
24の...と聞くと我々は大バッハの《平均律クラヴィーア曲集》、それに対するショパンの美しくも大胆な回答である《24の前奏曲集作品28(1839)》を思い起こす。ドビュッシーの《前奏曲集第1集(1910)》は明らかにショパン作曲の《前奏曲集》の延長線上に位置するものである。しかし、ドビュッシーの《前奏曲集》を一層個性的で輝かしいものにしているのは、むしろフレンチバロックの巨匠、フランソワ・クープランやジャン=フィリップ・ラモーの残したクラヴサン(チェンバロ)曲集への敬意があってのことだ。様々な舞曲や、思わせぶりな「タイトル」を一見無造作に並べるクラヴサン曲集の伝統は後期フレンチバロックの誇る遺産であり、ドビュッシーがその作曲技法だけでなく精神(エスプリ)に発想を求めていた事は想像に難くない。ラヴェル作曲の傑作《クープランの墓(1919)》に9年も先んじてのことである。《前奏曲集第1集》では、古代ギリシャ神話や、様々な国の風景や伝説に発想を求め、それらを入念に調査しながらも、空想的で挿絵(さしえ)的な“前奏曲”の雰囲気に仕上げている。初期フレンチバロックにおいて、前奏曲を弾くということは、様々な舞曲で構成される組曲を弾き始める前に即興的に和音をならしてチェンバロやリュートの調律の具合を確かめつつ、奏者の趣味をさりげなく披露する役目もあったという。しかしドビュッシーの前奏曲のあとに続くべき肝心の組曲は誰も聞くことはできない。それとは逆に、なぜバッハが《6つのフランス組曲》に本来そこにあるべき前奏曲を書かなかったのかも謎のままである。古代の舞姫たちが輪になって踊るサラバンド(デルフィの舞姫)、凶悪なまでの西風が吹き抜けるトッカータ(西風の見たもの)、南の国にしか無い鮮烈な日差しが踊るタランテラ(アナカプリの丘)、海からゆっくり浮かび上がる伝説のイスの街(イゾルデが生まれた街だ!)の大聖堂と僧侶が歌うグレゴリオ聖歌(沈める寺)… これ以上本日のお客様の想像力を奪ってしまうのはやめておこう。これら12曲のタイトルが「標題(プログラム)」として曲の頭に付けられてはおらず、全て曲の最後の部分に括弧書きで、謎めいた「...」が書かれていることは意義深い。タイトルの表すイメージに対して聴き手やピアニストが持つ想像力。ドビュッシーは、わたしたちの月並みな想像力に対する「注釈」を、前奏曲という形で書いてくれたのかもしれない。
flier backside

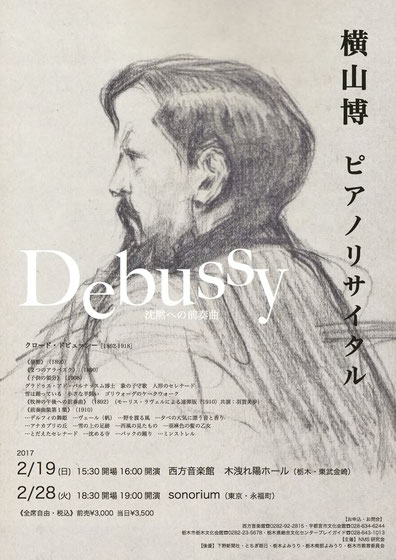




コメントをお書きください